糖尿病とは
糖尿病は「糖が尿にでる病気」 と読めますが、 医学的には、血液中のブドウ糖(血糖)が多くなる病気のことを言います。
ブドウ糖はからだにとって一番大切なエネルギーです。 脳の神経細胞もブドウ糖がなければ働けません。 血糖の濃度(血糖値)は、体温や血圧などと同じく、ある一定の範囲におさまる仕組みになっています。 この仕組みがおかしくなり、血糖値が健常な範囲を超えて上昇する(高血糖)のが糖尿病です。 皿糖値が高いのはエネルギーがたくさんあるのでなく、ブドウ糖の利用がうまくで
きず、血液中にあふれている状態です。あふれたブドウ糖が、 尿に漏れだすと「糖尿」の状態になります。 軽症の糖尿病の人では、尿に糖が漏れないこともあり、尿検査だけでは糖尿病であるかどうかの診断はできません。糖尿病は、健常人より高くなった血糖値によって診断されます
健常人の空腹時血糖値は 110 mg/dl 未満 糖尿病型の判定は 空腹時血糖値が 126 mg/dl 以上 随時血糖値が 200 mg/dl 以上 HbA1cが 6.5%以上
★HBA1C(ヘモグロビン·エー·ワンシー)とは
この検査値は、検査の時から1~2か月前までの期間の平均血糖値を示すも
のです。正常値は 4.6~6.2%です。
血糖値が高くなる理由
糖尿病では、なぜ血糖値が高くなるのでしょうか?それは、血糖を下げる「インスリン」というホルモンの働き(作用)が不足しているからです。インスリンは、膵臓(胃の裏側にある)から、血糖値に心して血液中に分泌されています。ご飯やパン、麺類などのいわゆる主食といわれる食品は、胃や腸で消化されるとほとんどがブドウ糖になります。その他の多くの食品にも、プドウ糖が含まれています。食事をすると血糖値が上昇し、それに応じて直ちにインスリンが分泌され(追加分泌)、ブドウ糖を肝臓、筋肉、脂肪といった組織に取り込ませて利用させるため、健常な人では食後でも140mg/dlを超えることはまずありません。一方、夜中など何も食べないのに早朝に血糖値が下がりすぎないのは、肝臓からブドウ糖が常に放出されているためです。この肝臓からのブドウ糖放出が多くなりすぎないように、絶食中もわずかの量のインスリンは絶えず分泌されています。(基礎分泌)
糖尿病では、このインスリンの基礎分泌、追加分泌が種々の程度で障害される結果、血糖値が上昇します。①インスリンの分泌が悪い(インスリン分泌不全)が主な人の他に、②インスリンの効きが悪い(インスリン抵抗性)ために血糖が上昇する人もあります。どちらの原因が強いかは、患者さんごとに異なるため、治療の際に考慮する必要があります。


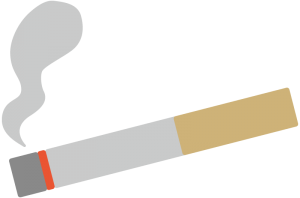








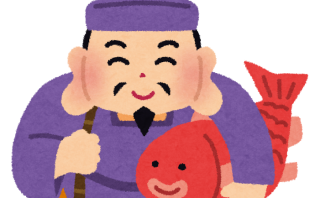





コメント