合併症とは
糖尿病合併症とは、糖尿病に関連しておこってくるいろいろな身体の障害のことです。
糖尿病の合併症には、 昏睡などの急性の合併症と、長期間(数年以上)高血糖にさらされている間に引き起こされる慢性の合併症とがあります。ここでは、主に慢性の合併症について述べます。
慢性の合併症には、糖尿病に特有のものと、糖尿病に特有ではないけれど、 糖尿病に合併しすいものの二種類があります。糖尿病に特有のものは、いわゆる糖尿病の3大合併症といわれるもので、
ことです。次の3つをいいます。
| 眼の合併症 | 糖尿病網膜症 |
| 腎臓の合併症 | 糖尿病腎症 |
| 神経の合併症 | 糖尿病神経障害 |
この3大合併症は、高血糖の期間が長ければ長いほど高頻度に出現してくるものであり、合併症というより、 糖尿病そのものといったほうがいいかもしれません。
これに対して、糖尿病の人に合併しやすい病気として、心筋梗塞や脳梗塞に関係する動脈硬化症があります。 動脈硬化症は糖尿病でなくても高血圧や脂質異常、喫煙などと強く影響しますが、 糖尿病であれば動脈硬化症の発症りリスクが大幅に増えます。
医学が進歩した今日でも、一度生じた合併症の治療は非常に難しいものです。ですから、合併症を治療するよりも、合併症を予防することが最も大切です
もしも合併症が生じてしまったとしても、それ以上に悪化させないことが重要です。糖尿病治療の目標は、血糖値を正常に近づけることですが、これは合併症を予防し、すでにある合併症の悪化を防ぐことを第一の目的としています。合併症を予防し、早期発見するためにも、合併症とはどのようなものであるかをよく知っておきましょう。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、 糖尿病の合併症の中で、最も日常生活に影響を与えるものの一つです。「網膜」は眼球の一番奥にあり、レンズをとおして見たものが像を結ぶところです。この「網膜」 が傷むのが網膜症で、網膜にある毛細血管という細い血管に変化が起こることにより生じます。 網膜症は以下の様に段階を追って進行していきます。
| 正常な網膜 | 単純網膜症 | 増殖前網膜症 | 増殖網膜症 | |
| 受診頻度の目安 | 1年に1回 | 3~6ヶ月に1回 | 1~2ヶ月に1回 | 2週間~1ヶ月に1回 |
| 自覚症状 | なし | なし | なし | 視力の低下黒い点が見えるなど |
| 治療 | 良好な血糖コントロール | 良好な血糖コントロール | 良好な血糖コントロール | 良好な血糖コントロール |
| 光凝固療法 | 光凝固療法 硝子体手術 |
糖尿病網膜症は高血糖が続くほどあらわれやすく、糖尿病と診断された時点で、すでに網膜症が認められる場合も少なくはありません。
網膜症には早期発見、早期治療が特に有効です。糖尿病の患者さんは、眼底検査を受け、異常がないかどうかを確かめなければなりません。そして、異常がなくとも、1年に1 回は眼底検査を受けることが勧められています。単純膜症の段階では、血糖コントロールをきちんとすれば元通りになおることがあ
ります。進行した網膜症の人では失明の可能性もあるため、内科たけでなく眼科の先生の診察も、定期的に受ける必要があります。手遅れにならないように、眼底検査は必ず定期的に受けるようにしましょう。
多くの糖尿病の患者さんを対象にした調査で、血糖コントロールが厳格であればあるほど、網膜症の出現や、すでにある網膜症の悪化が減ることがわかっています。できるだけ正常に近い血糖値を達成するように努力し、合併症が生じる危険を減らしましょう。
糖尿病腎症
腎臓は、血液中の老廃物を取り除く、 体のろ過装置です。 腎臓の糸球体を血液が流れる間に、水分と不要なゴミがこしだされて尿となり、糖やミネラルなどの必要なものは元の血液にもどされる作業が行われています。 高血糖が続くと、糸球体の毛細血管が障害され、老廃物が血液内に残ったり、蛋白質がもれやすくなったりということがおこります。
糖尿病腎症では、他の合併症と同じように、最初のうちは症状がありません。しかし、詳しく尿を検査すると、蛋白の一種であるアルブミンがでていることがわかります(早期腎症期)。これを放っておくと、アルプミンの量がだんだんと増え、普通の検査でも尿に蛋白が出ていることがわかるようになります(顕性腎症期)。蛋白尿が増えてくるようになると、 疲れやすい、体がむくむといった症状が出るようになり、高血圧や貧血を合併したりします。さらに進むと、体に溜まった老廃物が尿から出せなくなって尿毒症となり(腎不全期)、 最終的に血液透析が必要になります(透析療法期)。わが国で新たに血液透析が必要になる人は、年間3万人以上ですが、その原因疾患の第1位は糖尿病で、年間1万人以上です。
腎症でも早期発見、早期治療が特に有効です。 多くの糖尿病の人を対象にした調査で、血糖コントロールが厳格であればあるほど、腎症の出現や、すでにある腎症の悪化が減ることがわかっています。 できるだけ正常に近い血糖値を達成するように努力し、腎症の危険を減らしましょう。 また、腎症では血圧のコントロールが大変重要です。高血圧を避けるため、塩分摂取は控えめにしましょう。さらに腎症が進んだ段階では、腎機能保護に配慮した低蛋白食という食事が必要となり、それまでの食事内容と大きく変わることになります。このような場合には、くわしい内容をあらためて主治医や栄養士と相談するようにしましょう。
| 病期 | 尿アルブミン値(mg/g·Cr) あるいは 尿蛋白値(g/g·Cr) | 糸球体ろ過量 GFR(eGFR) | |||
| 第1期 | 腎症前期 | 正常アルブミン尿 (30 未満) | 30 以上 | ||
| 第2期 | 早期腎症期 | 微量アルブミン尿 (30~299) | 30 以上 | ||
| 第3期 | 顕性腎症期 | 顕性アルブミン尿(300 以上) あるいは 持続性蛋白尿(0.5 以上) | 30 以上 | ||
| 第4期 | 腎不全期 | 問わない | 30 未満 | ||
| 第5期 | 透析療法期 | 透析療法中 | – |
糖尿病神経障害
神経は、からだじゅうに張りめぐらされた電気の配線のようなものです。脳からからだのすみずみに指令が運ばれ、逆にからただの先端からは脳に情報が伝達されます。高血糖が続くと、この神経網に障害を生じます。はじめは手や足の指先に症状が出やすく、 足先の痛み、ほてり、冷感、しびれ感(ぴりぴりした感じや、じんじんした感じ)などとして自覚されます。 また、熱いとか痛いという感覚が感じられなくなり、やけどをしたり怪我がひどくなったりしやすくなります。自律神経とよばれる神経も障害されやすく、立ちくらみ、がんこな便秘や下痢、排尿障害、 ED (勃起不全) といった症状があらわれることがあります。
神経障害を発症してすぐであれば、血糖コントロールの改善や内服治療によってしびれなどの症状を和らげることができます。しかし、症状が出現してから長い期間を経た場合には、 治りにくいことが多いので、日頃から血糖コントロールをよくしておくことが大切です。 神経障害も、血糖コントロールが良好であればあるほど、発症の危険性を減らせることがわかっています。
動脈硬化症
糖尿病では細小血管障害 (三大合併症)だけでなく、大血管の障害もきたしやすくなります。全身の血管が狭く、詰まりやすくなる動脈硬化症は、年をとるにつれて起こりやすくなります。 糖尿病の患者さんは、動脈硬化が進行しやすく、心臓病(狭心症、 心筋梗塞など)に2~4倍なりやすく、脳卒中(脳梗
塞、脳出血など)に約5倍なりやすいとされています。
糖尿病だけではなく、高血圧症 脂質異常症 ·肥満症 喫煙習慣も動脈硬化の原因になります。 糖尿病にこれらの疾患が併存すると動脈硬化症をおこす危険性がより高くなるため、糖尿病以外の病気についても改善をめざす必要があります。 肥満(特に内臓脂肪の蓄積)があると、糖尿病 高血圧症 脂質異学
症が一人の患者さんに重なって認められることがよくあります(この状態をメタボリックシンドロームといいます)。“メタボ”の患者さんは、体重減量によって糖尿病·高血圧症·脂質異常症を一網打尽に治療できる可能性があります。動脈硬化予防の目標は、食事療法·運動療法による体重管理(減量)、血糖
管理、血圧管理、脂質管理、禁煙の5つです。特に喫煙は動脈硬便化の進行に強い影響を及ぼすため、禁煙されるにとを強くおすすめします。 なかなか自分の意志だけでは禁煙できない患者さんは、禁煙外来なども利用してください。
【メタポリックシンドロームの診断基準】
内臓脂肪蓄積 ウエスト周囲径 男性≧85cm 女性≧90cm
(内臓脂肪蓄積 男女とも100㎠に相当)
上記に加え以下の2項目以上
1) 中性脂肪≧150mg/dL かつ/または HDL-C<40mg/dL
2)収縮期血圧≧130mmHg かつ/または 拡張期血圧280mmHg
3)空腹時血糖≧110mg/dL
「メタボリックシンドローム」って、なに?
「内臓脂肪の蓄積」を上流にもち、生活習慣病を複数発症した状態のことを「メタボリックシンドローム」といいます。
脳の血管が狭くなる
脳卒中とは、脳出血や脳梗塞 (脳血栓と脳塞栓)など、脳の血管に起因する病気のことです。いずれも動脈硬化と深い関係があります。脳血管障害がおこると、その脳の領域に関連した機能が障害されます。 会話ができない、手足の麻痩をきたすなどの症状があり、場合によっては命を落とすこともあります。
脳梗塞は日本人の死因全体の第4位です。脳梗塞のなりやすさを調べる検査に頚動脈エコーがあります。
脳卒中とは?
脳梗塞(脳血栓・脳塞栓)・脳出血・クモ膜下出血・一過性脳虚血発作
心臓の血管が狭くなる
心臓は、体内に血液を送るポンプの働きをしています。心臓には、心臓の筋肉に血液を送るために冠動脈という血管があり、この冠動脈にも動脈硬化が生じます。冠動脈が細くなると、心臓の筋肉は酸素や栄養分を十分に送ってらえない状態になり、運動時などに胸痛としてあらわれます。これが狭心症です。冠動脈が完全につまってしまうと、心臓の筋肉は酸素不足で障害され、心筋梗狭心症と心筋梗塞
塞となります。心筋梗塞は日本人の狭心症死因全体の第2位です。
冠動脈の硬化度や心臓の働き具合を調べるためには、心電図·心臓エコー·心臓 CT、そして冠動脈造影
検査(カテーテル検査)などの検査があります。
糖尿病足病変
糖尿病足病変には、足の指の間や爪の白癖菌症(はくせんきんしょつ)か靴ずれや胼胝(たこ)、足の潰癌(かいよう)、そして糖尿病性足壊症(えそ)が含まれます。足病変が足壊症まで進行すると治癒は難しく、残念ながら足や下肢の切断が避けられない場合が少なくありません。
糖尿病性足壊痕の主な原因は、①末梢神経障害、②血流障害、③細菌への抵抗力減弱の3つです。
① 未梢神経障害があると、 靴ずれができても、併が大きくなっても、患者さん自身は痛みを感じにくくなるため、しばしば足病変の発見や手当てが遅れます。発見や手当てが遅れれば、小さな傷が潰癌に、潰島は壊痕に進行しがちです。
②血流障害(閉塞性動脈硬化症など)では、 足の太い血管が、動脈硬化により狭くなったり、つまったりします。 足への血液の流れが悪くなり、冷たく感じたり、痛みを感じたりします。 完全に血液の流れが途絶えてしまうと、足が壊痕となるため、切断を余儀なくされることになります。
③ 糖尿病患者さんは細菌への抵抗力が減弱しており、 足の潰島が化膿しやすく治癒が遅くなります。
しかし、この3者がそろったからといって、ただちに足壊痕になるわけではありません。日頃から、靴ずれ·やけどなど足の怪我に気をつけること、足を清潔に保つフットケアが大切です。
歯周病
歯周病は歯周病菌による歯周(歯の根っこの歯茎)の慢性的な炎症をさし、糖尿病の重大な合併症の1つです。歯周病にかかると出血や口臭の原因となり、さらに進行すると歯がグラグラするようになり、最終的には歯が抜けてしまう原因にもなります。
糖尿病にかかると細菌を攻撃する白血球の働きが落ちるため、歯周病が重症化すると言われています。 従って糖尿病治療は歯周病治療にもつながることになります。一方で歯周病治療をしっかり行うことによって血糖コントロール状態も改善することが報告されています。 歯科治台療も是非並行して行うようにしてください。
認知症
認知症は記憶能力の低下など生活の質を著しく低下させる疾患です。近年の研究により、糖尿病の患者さんはアルツハイマー病と血管性認知症のどちらにも罹患しやすいことが知られるようになりました。高血糖だけでなく、低血糖にも認知症進行のリスクになりますので、低血糖の無い範囲で血糖値を可能な限り良好に保つことが、認知症を発症することや認知症が進行するのを防ぐために重要です。



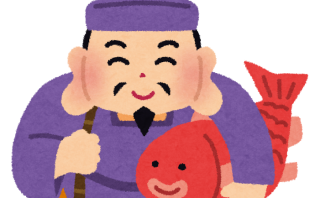













コメント