糖尿病治療の原則
糖尿病の治療で、血糖値をできるだけ正常に近づけることを、「糖尿病(血糖値)をコントロールする」といいます。糖尿病でよいコントロールを保つには、食事療法、運動療法、薬物療法の 3つをうまく組み合わせることが大切です。
実際に、自分にはどのような治療が必要で、食事、運動、そして薬は、どんなものがどれくらい必要か、といったことを主治医とよく相談して下さい。糖尿病といっても、どのような治療が向いているのかは、人によって異なっています。
糖尿病の治療の目標は、血糖値をできるだけ正常に近づけることです。 正常に近づければ近づけるほど、糖尿病の合併症が生じる危険性を減らすことができます。健常な人では空腹時血糖:110mg/dl 未満、HbA1c:4.6~5.5%に保たれています。 しかし、 使っている薬の内容や年齢、活動レベル次第では、無理に「正常」レベルまで下げようとすると低血糖を引き起こし、かえって良くないことがあります。
それぞれに合ったコントロール目標について、主治医と話し合いましょう。
糖尿病は、風邪などのように放っておいても自然になおる病気とは違って、必ず医師の管理が必要です。 面倒がらずに診察や検査を受け、どのように治療を進めていけばよいか、話し合うようにしましょう。自己流の治療や、自分の判断で治療をやめたりすることは禁物です。
糖尿病治療の目標
糖尿病合併症の予防のため血糖コントロールを行いますが、その目標値は患者さんの年齢、治療法、他に持っている病気、体力などによって異なります。一般的に元気で若い患者さんは空腹時血糖: 130mg/dl 未満、食後血糖:180mg/dl 未満、HbA1c:7%未満が目標となります。
しかし、あまり厳しすぎるコントロールをすると逆に低血糖やそれに伴う不都合が生じることがあるので、特に高齢(65歳以上)の患者さんの場合は少し緩めの目標値が設定されています。いずれにしても、患者さんそれぞれで目標値が異なりますので主治医とよく話し合いましょう。
表1 血糖コントロール目標
—コントロール目標値(注4)—
| 目標 | 血糖正常化を 目指す際の目標(注1) | 合併症予防 のための目標(注2) | 治療強化が 困難な際の目標 目標(注3) |
| HbA1c(%) | 6.0未満 | 7.0未満 | 8,0未満 |
治療目標は年齢,確病期間, 臓器障害,低血糖の危険性, サポート体制などを考慮して個別に設定する。
- 注1)適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合, または薬物療法中でも低血糖など
の副作用なく達成可能な場合の目標とする。 - 注2)合併症予防の観点からH6A1Cの目標値を7%未満とする. 対応する血糖値としては, 空
- 腹時血糖値130mg/dL未満, 食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。
- 注3)低血糖などの副作用, その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
- 注4)いずれも成人に対しての目標値であり, また妊娠例は除くものとする。
表2 高齢者糖尿病のコントロール目標
| 患者の特徴 健康状態注1) | カテゴリーI ①認知機能正常 かつ ②DADL自立 | カテゴリーII ①軽度認知障害~軽度認知症 または ②手段的ADL低下, 基本的ADL自立 | カテゴリーIII ①中等度以上の認知症 または ②基本的ADL低下 または ③多くの併存疾患や 機能障害 |
重症低血糖が危恨される薬剤(インスリン製剤、SU薬、グリニド薬など)の使用
| なし 注意2) | 7.0%未満 | 7.0%未満 | 7.0%未満 | 8.0%未満 |
| あり 注意3) | 65歳以上 75歳未満 7.5%未満 (下限6.5%) | 75歳以上 8.0%未満 (下限7.0%) | 8.0%未満 (下限7.0%) | 8.5%未満 (下限7.5%) |
食事療法の原則
各人が必要とするエネルギー量は、年齢、性別、 運動量などによって異なっています。同じ体格であっても成長期の人、運動選手、 激しい肉体労働をする人は多くのエネルギーを必要としますし、運動量の少ない人は、さほどのエネルギーを必要としません。適正なエネルギー量を算定する原則をお示しします。
① 標準体重
まず、あなたの標準体重を求めます。
標準体重(kg) =身長(m)×身長(m) ×22
これは、Body Mass Index (BMI) という体重の指標が、22のとき、もっとも適正であるという事実に基づいています。 BMI は、体重 (kg) – {身長(m) ×身長(m)} から計算される数値です。なお、この BMI が、25を超えると肥満と判定されます。
例)身長16Ocmの方の標準体重: 1. 6 (m) ×1.6×22=56. 3 (kg)
②適正なエネルギー量上記で求めた標票準体重1kgあたり、
- 軽労働では 25~30kcal
- 中労働では 30~35kcal
- 重労働では >35 kcal
をかけた数値が、基本的な必要エネルギー量です。 さらに、年齢·性 肥満度などを考慮して、主治医、栄養士とあなた自身が、自分にとってもっとも適正なエネルギー量を決定してください。
例)普段は事務作業をしている身長160cmの患者さんの場合、
- 56.3 (kg) x 25 (kcal)= 1,40O(kcal)から
- 56.3 (kg) x 30 (kcal)= 1,680 (kcal)の間
糖尿病と妊娠
~妊娠糖尿病とは~
妊娠中に発症または初めて発見された糖尿病に至っていない糖代謝異常。 つまり糖尿病ではありませ
んが、正常よりは血糖値が少し高い状態をいいます(診断基準参照)。妊娠中は少しの高血糖でも、 赤ちゃんやお母さんに影響がありますので、より厳しく血糖管理が必要となるため、妊娠糖尿病という新しい病状(病期)が設けられました。妊娠前から既に糖尿病であることが判っている場合は、「糖尿病合併妊娠」と呼ばれます。 糖尿病が妊娠中に判明した場合、従来は妊娠糖尿病と呼ばれていましたが、「妊娠時に診断された明らかな糖尿病」と呼ぶように改められています。 妊娠糖尿病のお母さんは、将来に2型糖尿病を発病する危険性が高いため、出産後も糖尿病について注意する必要があります。
どうして起こるの?
胎盤から出るホルモン (ヒト胎盤ラクトーゲン、エストロゲン、プロゲステロン、プロラクチンなど) がインスリンを効きにくくしたり、胎盤でインスリンが分解されたりすることにより、血糖が上昇して妊娠糖尿病を発症します。
特に①糖尿病の家族歴がある、②肥満、 ③35 歳以上、④妊娠糖尿病の既住、⑤尿糖陽性、⑥巨大児分娩歴、 ⑦原因不明の流早産·死産、③原因不明の先天異常児分娩既往をもつ場合は、注意が必要です。
赤ちゃんやお母さんへの影響は?
まず、赤ちゃんへの影響ですが、 赤ちゃんの器官が形成される妊娠初期にお母さんの血糖が高いと先天異常児が生まれてくる確率が高くなります。また妊娠中に高血糖状態が続くと、 ブドウ糖が胎盤を通過し、赤ちゃんが高血糖状態となります。高血糖を是正しようとして赤ちゃんの膵臓からインスリンがたくさん分泌されますが、その結果、 巨大児になったり、分娩直後の赤ちゃんに低血糖を認めたりすることがあります。その他、高ピリルビン血症、低カルシウム血症、多血症などがみられることもあります。お母さんへの影響としては、 感染症 流早産·妊娠中毒症などがあります。
また巨大児で難産となった場合、 赤ちゃんの神経を傷つけたり、場合によっては帝王切開になることもあります。
治療は?
食事療法、運動療法(激しい運動、腹圧のかかる運動は除く)、薬物療法です。ただし薬物療法に関し
ては、内服薬は胎児への安全性が十分確立されていないため、インスリン療法を行います。
血糖コントロール目標は、食前血糖:100mg/dl以下、食後2時間血糖:120mg/dl 以下、 HbA1c:5.8%以下と厳格な血糖管理が要求されます。
産後は?
妊娠糖尿病では、産後1~3ヵ月後に再評価を行います。 正常化していることがほとんどですが、 糖尿病型·境界型の場合は、 産後も血糖管理が必要です。
一旦、正常化しても数年後に糖尿病と診断されることがあるため、1年に1回は検査を受けることをお勧めします。
[参考]妊娠糖尿病の診断基準
75gプドウ糖負荷試験で、次の基準を1つでも満たした場合に診断します。
1)空腹時血糖値が、92 mg/dL 以上
2)負荷後1時間の血糖値が、180 mg/dL 以上
3) 負荷後2時間の血糖値が、153mg/dL 以上



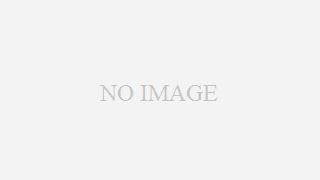







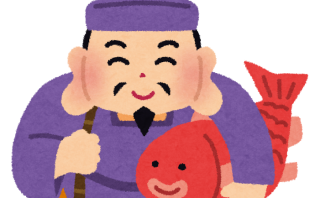





コメント